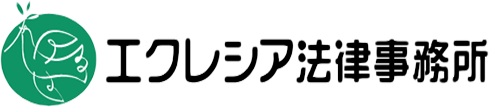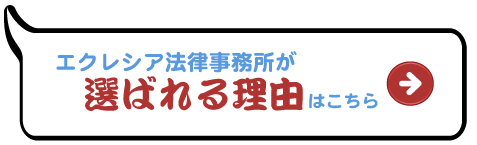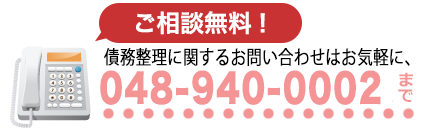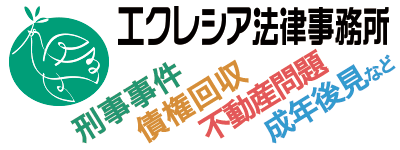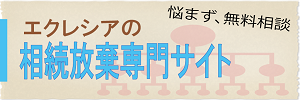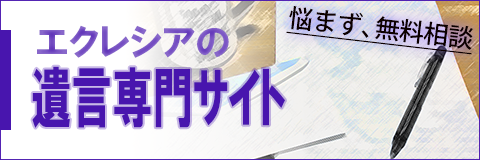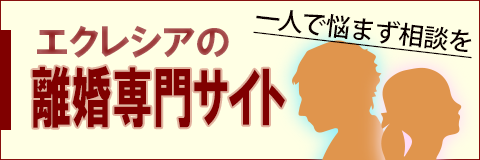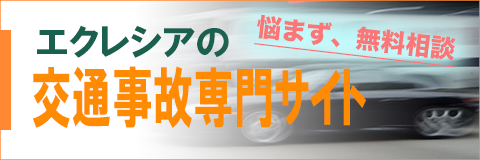難しいといわれる個人再生手続きを
5分で分かる
ようにまとめてみました!
個人再生手続きの最大の特徴
個人再生手続の最大の特徴は、
債務者の債務を『大幅に減額』できる
この一言に尽きます。
借金苦に悩む人には、朗報ですね。
個人再生手続の種類
個人再生手続には、
「小規模個人再生」
「給与所得者等再生」
の2種類がありますが、実務では「給与所得者等再生」は稀で、ほとんどが「小規模個人再生」です。両者の大きな違いは、「手続き利用要件」、「返済金額要件」と「議決要件」です。
※「給与所得者等再生」は、「議決要件」との絡みで、弁護士が個人再生遂行の観点から戦略上とる手続きになっているのが実情です。
そこで、個人再生を考えている方は、まず、
「手続利用要件」と「返済金額要件」
を理解しましょう。
なお『住宅ローン』を抱えている方のために、個人再生をする場合でも住宅を維持できる特則として
「住宅資金特別条項」
がありますので、住宅ローンのある方は、合わせて
「住宅資金特別条項」
を理解してください。
個人再生手続き利用要件
「債務総額要件」と「収入要件」があります。
1 「債務総額要件」:債務の総額が5000万円以下であること(住宅ローン等を除く)
債務が5000万円以下であれば、200万円でも300万円でも利用可能です。制限はありません。
※当事務所でも200万円前後のケースは多数あり、500万円以下の方が、半数を占めます。
《当事務所受任事件の債務額状況》
(債務額) (件数)
300万円以下 102件(24%) 300万円~500万円 120件(27%) 500万円~1000万円 144件(33%) 1000万円以上 70件(16%) 過去20年間
因みに最少額は、77万円で、最高額は、4,490万円の方でした。
2 「収入要件」:将来継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること
要は、分割返済していくだけのきちんとした収入が必要ということです。サラリーマン、パート、アルバイトの方や現在働いていなくても、内定をもらっているなど就職の見込みのある方でも利用できます。
※この要件は裁判所で意外と厳しく審査され、収入が少なすぎたり不安定だと手続きが認められないこともあります。
なお、自営業者は「小規模個人再生」なら利用できますが、「給与所得者等再生」は利用できません。
個人再生での返済金額要件
では再生手続きが利用できるとして、債権者にいくら払う必要があるのでしょうか。
「最低弁済額」と「清算価値」のうち、いずれか高い方の金額以上
を弁済することが要件となります。
別の表現をすると、債権者には
「最低弁済基準額」
を払えばいいのだが、もし、あなたの「清算価値」が「最低弁済額」を超えた場合、つまり
「清算価値」>「最低弁済額」
の場合は、債権者には
「清算価値」相当額
を払わなければならない、ということです。
※「最低弁済額」と「清算価値」という重要なワードが出てきました。この2つを必ず理解してください。
「最低弁済額」とは、債権者に払わなければならない最低限度の金額のことで、債務額に応じて決められています。
「清算価値」とは、あなたの保有財産のうち一定の控除をした残りの金額のことです。 ← 債権者にはこの金額以上を払わなければなりません。
最低弁済額の詳細は 👉最低弁済額
清算価値の詳細は 👉清算価値
「給与所得者等再生」での注意点!
冒頭で、個人再生手続には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があると説明しましたが、「給与所得者等再生」の場合は、さらに
「可処分所得の2年分」以上という要件が加わりますので注意してください。
要注意!
「給与所得者等再生」では、
「最低弁済基準額」、「清算価値」、「可処分所得の2年分」のうち最も高い金額以上
を弁済することが要件となります。
※通常「可処分所得の2年分」の金額が最も高くなりますので、あえて「給与所得者等再生」を選択する必要はありません。冒頭で、『実務では「給与所得者等再生」は稀で、ほとんどが「小規模個人再生」です。』と説明したのはこのためです。
👉 可処分所得 はこちら
個人再生の議決要件
小規模個人再生では、
債権者総数の『半数以上』かつ『債権総額の2分の1以上』の債権者から反対されないこと
が要件となっています。
反対されたらどうなるの?
債権者からの反対が、総債権者の半数または総債権額の半額に達した場合は、
再生手続きは廃止(終了)
となり、自己破産や任整理等別の方法での債務整理を検討せざるを得えなくなります。
実務の現状では、ほとんどの金融機関は反対をしてきませんが、保証会社、政府系金融機関や一部の銀行はたびたび反対してくることがあります。
対策はありますか?
反対する金融機関が債権者の過半数を占めている場合や債権額の2分の1以上となっている場合は、
「給与所得者等再生」
を検討することになります。
というのは、「給与所得者等再生」では、債権者の反対・異議があっても、
裁判所が相当と認めれば再生計画が認可
されるからです。